つむぎの取り組み
Serviceこども支援
療育スキルアップ指導
発達支援ネットワークつむぎでは、こどもたち一人ひとりに合った支援の質をさらに高めるため、川崎医療福祉大学の諏訪利明先生による「療育スキルアップ指導」を実施しています。
実際の支援の様子を見ていただきながら、支援の組み立て方やかかわり方について専門的な視点からアドバイスを受ける、貴重な学びの機会です。また、指導内容は全事業所をオンラインでつなぎ、リアルタイムで共有。ひとつの現場で得た学びを法人全体で活かしています。
巡回相談の実施
支援の質をさらに高める取り組みの一つとして、理事長による巡回相談を実施しています。支援に難しさを感じているこどもへの関わりについて、実際の場面を理事長が直接確認し、職員とともに支援内容を振り返ります。チーム全体でよりよい支援を目指す機会となっています。
公開療育の実施
法人全体で支援の質を高め合うことを目的に「公開療育」を実施しています。管理者が各事業所を訪問し、支援の様子や環境、職員連携などを多角的に観察。良い実践の共有や改善点の整理を行い、Zoomを通じて全事業所で学び合う仕組みを整えています。
職員学習会・実践発表会の実施
つむぎでは、職員の専門性向上のために学習会を定期開催。出張報告、事例検討、テーマ発表などを通して実践を深めています。また、2年目以降の職員を対象とした「実践発表会」も毎年2月に開催。目標管理活動でのテーマに沿った実践を報告し合い、学びを法人全体へ共有しています。
支援会議の実施
週1回の支援会議では、児童発達支援管理責任者を中心にこどもの成長や支援の方向性を確認。困りごとを一人で抱え込まず、チームで共有しながら支援の質と職員の安心感を両立させています。
連絡会の実施とICTの活用
毎日の連絡会で、その日の支援内容や注意点を職員間で共有。情報はクラウド型ツール「WAWAオフィス」にも記録し、出席できなかった職員も確認可能。ICTを活用して情報の一元化と連携を図っています。
未来の支援者をめざすあなたへ
「現場で学び、現場で育つ」。それが、つむぎの支援スタイルです。
発達支援ネットワークつむぎでは、支援の質を高めるための取り組みを職員全体で共有し、こども一人ひとりと丁寧に向き合う支援を行っています。日々の支援の中で仲間と悩みを共有し、学び合い、成長していくことができる環境があります。こどもや家族、地域とつながりながら、「誰かの力になりたい」という思いをかたちにしていく仕事です。教育・福祉・心理など、人の成長に関心がある学生の皆さん、ぜひ一度、つむぎの現場をのぞいてみてください。
家族支援
親子サポート教室
児童発達支援を利用するご家庭を対象に、月1回土曜日に親子サポート教室を開催。普段の活動の様子を見ていただいたり、親子で制作・季節のプログラムに取り組んだりしています。
子育て・親育ち ハッピーサークル
保護者同士がつながり、学び合える場として「ハッピーサークル」の事務局を担い、座談会・学習会・講演会などを実施。公式LINEにご登録いただくと、イベント情報が届きます。

ペアレントトレーニング
ハッピーサークル学習会の一環で毎年実施。こどもの行動理解や関わり方を学び、家庭での子育てに役立てる内容です。
相談支援ファイル書き方講座
保護者とともにこどもの成長を振り返りながら、相談支援ファイルの記入・整理を行う講座です。多機関で情報を共有するための大切なツールとして、講座後には座談会も実施しています。
ひだまりネット(不登校のこどもを持つ親の会)
不登校のこどもを持つ保護者の会「ひだまりネット」の事務局を担い、奇数月は吉備中央町、偶数月は高梁市で座談会を開催。同じ立場の保護者がつながり、安心して語り合える場づくりを大切にしています。詳細・申込は公式LINEから。
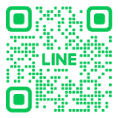
地域支援
みんなの食堂「たまりば高梁」
毎月第3土曜日、高梁市の複合施設ポルカで実施。こどもから大人まで誰もが参加できる地域の居場所として運営。LINE登録で詳細・申込情報をご確認いただけます。ボランティア・寄付も募集中です。

みんなの食堂「たまりば吉備中央」
毎月第1土曜日、つむぎ吉備中央で実施。地域のつながりを育む居場所として、食事とふれあいの場を提供。こちらもLINE登録でご案内しています。

講演会の開催
年に2回、保護者・支援者・地域の皆さまと共に学ぶ講演会を実施。自閉スペクトラム症、学習症、不登校、愛着形成など、さまざまなテーマを取り上げています。情報はハッピーサークル公式LINEからご確認ください。
ケース会議の実施
幼児期には、保護者・こども園・保健師・家庭センター・療育機関・相談機関などと連携し、半年~年1回程度ケース会議を実施。こどもの成長や課題を共有し、地域で応援団をつくります。 小学校以降は、特別支援教育コーディネーターを中心に必要に応じて開催し、継続的な支援体制を整えています。

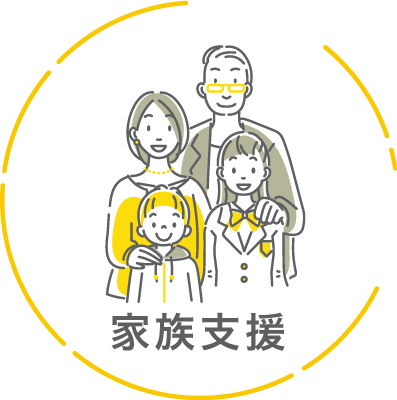
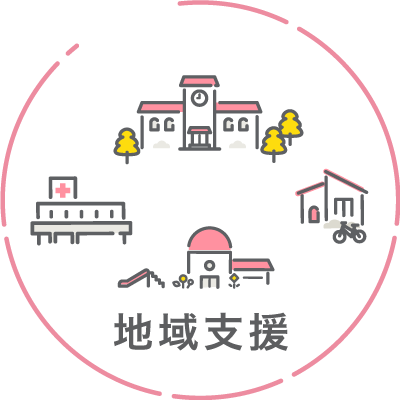
 Instagram
Instagram